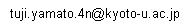|
 トップページ トップページ
|
 プログラム プログラム
|
 発表要旨 発表要旨
|
 アクセス アクセス
|
 宿泊 宿泊
|
 食事 食事
|
 そのほか そのほか
|
発表要旨
澤田晶子(京都大学 霊長類研究所)
多様なキノコを食べるニホンザル
ニホンザルは、学習によって食物レパートリーを獲得する。森林内にまばらに存在することが多いキノコは、その絶対量の少なさに加え、どこに生えているのか予測困難であることから、ニホンザルにとっては学習の機会が極めて少ない食物であると言える。菌類相の多様性が高く、毒性のあるキノコの分布も確認されている屋久島において、ニホンザルがどのようなキノコを食べているのだろうか。本研究では、ニホンザルが食べたキノコ・食べなかったキノコの分子種同定結果を基に、ニホンザルのキノコに対する選択・忌避の傾向とその基準について解明した。
調査の結果、キノコ食はニホンザルの採食時間のわずか2.2%を占めるにすぎないにもかかわらず、67種 (31属) という非常に多くの種のキノコが食べられていることが判明した。手には取ったが食べなかったキノコも含めると、その数は92種にのぼり、屋久島のニホンザルが極めて多様なキノコと関わる動物であることが示された。また、キノコ食をおこなう際に、ニホンザルが手に取ったキノコに対してにおいを確認する、あるいはかじって吐き出すという「検査行動」を取ることがあった。そこで、採食時の行動パターンを、ニホンザルがキノコに遭遇したとき・手に取ったとき・検査行動を見せたとき・食べたときと4段階に分けて解析した。その結果、検査行動なしですぐに食べるキノコは毒キノコである割合が低く、ニホンザルが途中で採食を止めたキノコは毒キノコである割合が高いことが判明した。一方で、検査行動によって毒キノコを効率的に回避できているわけではなく、ニホンザルはキノコについて完全な知識を持っているわけではないことが示された。
以上のことから、ニホンザルはキノコについてある程度の知識を持っているものの、味覚も重要な役割を果たしており、実際に食べてみることで、食べられるキノコなのかどうかその場で判断していると考えられる。
布施未恵子(神戸大学農学研究科 篠山フィールドステーション)
昆虫の生態を利用した霊長類の昆虫類探索・捕食行動
霊長類種の多くは、多かれ少なかれ昆虫類を捕食する。アイアイのタッピングなどの珍しい行動がみられる場合や、道具使用に関連するような場合は、多くの研究がなされている。昆虫を食べる時間割合が少ない霊長類では、種名までは明らかになっていないことが多く“虫”というカテゴリーで公表されている。昆虫を食べる時間割合が少ない場合でも、「なぜ少ない量でも昆虫を必要とするのか」という問いを立てるなどして検証することが可能である。だが、栄養分析はサンプル採取に時間を要するし、特殊な成分を抽出してもそれがもたらす効果を明らかにするにはこちらも時間を要するため、敬遠されているように思われる。昆虫類を食べる割合が多い種では、昆虫の詳細な種類と遊動域内の昆虫バイオマスの調査が行われたが、昆虫バイオマスだけでは昆虫選択が明らかにされなかった。昆虫バイオマスの調査にはかなりの労力が必要であり、栄養分析等と同様に敬遠される。これでは、「なぜ霊長類の生息環境に豊富に存在する昆虫類の中からある特定の昆虫を選択するのか」という問いの答えはえられない。
そこで本発表では、昆虫のバイオマス全体を調べるのではなく、よく利用する昆虫に焦点をしぼり、特定の昆虫の利用可能性と採食行動との対応から問いにアプローチする。具体的には、昆虫と植物のゆるやかな関係性を利用したチンパンジーの効率的なアリ捕食行動から、チンパンジーの昆虫選択に関する新たな知見を提供する。次に、生活場所(植物、地中、川のなか)や生活環(幼虫、さなぎ、成虫、繁殖虫)、性質(逃げ足の速さ、毒の有無、隠蔽の程度)、といった昆虫側の生態と、ニホンザルの昆虫類捕食行動から、特定の昆虫とその利用可能性を調べる方法について考える。最後に、霊長類と昆虫と植物という三者関係でとらえることでみえてくる、霊長類の生態系における役割について考察する。
Andrew J.J. MacIntosh(京都大学 霊長類研究所)
Epidemiology of nematode parasite infection in Japanese macaques: heterogeneity in the external and internal environments
One of the fundamental characteristics of parasite infection dynamics is that parasite distributions are typically aggregated across host populations; most of the hosts carry few parasites while few hosts carry most of the parasites. Understanding why such variation across hosts exists continues to be an active area of research in infectious disease epidemiology. My research is focused on investigating patterns of infection across hosts under natural conditions, using Japanese macaques on Yakushima (Macaca fuscata yakui) and their gastrointestinal nematode parasites as a single host-multiple parasite model study system. Japanese macaques across their range are infected by a total of 5 species of nematode parasite, but only the population on Yakushima is infected by all of them, as parasite diversity increases with decreasing latitude (Gotoh 2000). Each of these worms requires exposure to the external environment in order to complete its life cycle, but 2 general transmission strategies are employed: direct transmission and trophic transmission. Oesophagostomum aculeatum (Strongylida), Strongyloides fuelleborni (Rhabditida), and Trichuris trichiura (Enoplida) are directly transmitted nematodes that are acquired through ingestion of infective stage larvae or eggs encountered in the external environment. Streptopharagus pigmentatus and Gongylonema pulchrum (Spirurida) are trophically transmitted worms that are acquired through ingestion of an infected intermediate host; usually a coprophagous beetle. I will introduce these 5 species of nematode parasite and discuss how their transmission strategies, macaque behavior and physiology, and characteristics of the external environment all interact to determine observed infection phenotypes. The ultimate goal of this research is to uncover the mechanisms underlying parasite transmission and what this can tell us about the co-evolutionary histories of these natural enemy species.
座馬耕一郎(林原類人猿研究センター)
霊長類とシラミの関係
シラミは哺乳類全般に寄生する体長1〜3mmほどの吸血性の昆虫である。生活環のすべてを宿主の体表面でおくる性質があり、(1)宿主間の接触時に移動分散する、(2)宿主特異性が強い、(3)外部寄生虫であり宿主の行動でコントロールできる、といった特徴がある。これらの特徴は霊長類とシラミの関係を研究する上で鍵となっている。たとえばNicolle et al. (1909)はシラミが発疹チフスをヒトとヒトの間で伝播させることを解明し、Reed et al. (2004, 2007)はシラミと霊長類の分子系統を比較し宿主―寄生虫の進化史を明らかにしている。Tanaka & Takefushi (1993)は野生のニホンザルが毛づくろいでシラミの卵を除去していることを実証し、この結果をふまえ、Zamma (2002)は、ニホンザルとシラミの関係を、宿主―寄生虫の関係と、捕食者―被捕食者の関係の両側面から分析をおこなった。猿害で駆除されたニホンザルからシラミ卵の分布と密度を調べ、嵐山のニホンザルを対象に毛づくろいを調査したところ、ニホンザルはシラミ卵の多い背や腕、脚の外側をよく毛づくろいしていることがあきらかになった。また、毛の本数あたりのシラミ卵数や、かき分け回数あたりのシラミ卵除去数に部位間で差がなかったことから、シラミはニホンザルの捕食圧を逃れるように産卵していると推察された。シラミの増加率は1日に約12%と高く、ニホンザルが1日で除去する割合とほぼ同じであることから、シラミの増加を抑えるという生態的な要因が、毛づくろい相手と日常的に集団を作るというニホンザルの社会を作り上げている可能性が示唆された。宿主の体毛に隠れたわずか1〜3mmのシラミの生態を野外で(飼育下でも)研究するのは困難である。発表では野生チンパンジーに生息するシラミ卵の密度を推定する試みについても紹介する。
佐藤宏樹(京都大学 アフリカ地域研究資料センター) Hitoki Sato (Center for African area Studies)
マダガスカル熱帯乾燥林においてチャイロキツネザルが種子散布者として果たす役割の季節変化
(Seasonal variation in the role of the brown lemur as a seed disperser in a Malagasy tropical forest)
動物種子散布は、果実資源獲得による動物側の利益と、種子の空間分散で得る植物側の利益によって成り立つ相利的な共生であり、熱帯林では最も一般的な種子散布様式である。オセアニアを除く熱帯林の主要な樹上性果実食者である霊長類は、種子散布者としての役割を担っている。とくに大型果実食者はさまざまなサイズの種子を大量に、かつ広域に散布する可能性があり、多くの分類群で種子散布機能の定量評価が進められている。大型鳥類・哺乳類分類群の多くが欠如しているマダガスカルでは、キツネザル類の重要性が示唆されてきたが、その種子散布機能に関する長期データはこれまでに報告がなかった。
本発表の前半では、マダガスカル西部熱帯乾燥林における最大果実食者・チャイロキツネザルが果たす種子散布機能について評価する。1年間の観察、糞分析、発芽実験、植生調査から、個体群による大量散布(9854個/km2/日)や、摂食による種子発芽率の改善、チャイロキツネザルだけに散布を頼る大型種子植物が森林の主要な構成樹種であること(胸高断面積:32%)が明らかになった。 モンスーンの影響によって明瞭な雨季と乾季に分かれるマダガスカル熱帯乾燥林では、植物の結実パターンや動物の行動パターンも季節的に変化する可能性がある。本発表の後半では生態系の季節性に着目し、チャイロキツネザルの種子散布機能の変化について議論する。多くの植物種が水資源の豊富な雨季をピークに結実する。雨季はチャイロキツネザルの活動量も多いため、様々な種子をより遠くに運ぶ機能を示した(推定散布距離 91−245 m, percentile 25−75)。水資源が著しく制限される乾季は、数種の大型種子植物が結実ピークを示した。果実欠乏期に資源を提供するこれらの植物種は、唯一の散布者であるチャイロキツネザルの獲得に成功していると考えられるが、その推定散布距離は22−111 m (percentile 25−75)にとどまった。散布距離の縮小には体内水分の損失を防ぐために乾燥条件で活動性を低下させるチャイロキツネザルの行動戦略が関わっている。マダガスカル熱帯乾燥林では種子散布をめぐる動植物相互作用のパターンが、季節的な気候、とくに水資源量の変動によって著しく変化することが示された。
揚妻直樹(北海道大学 北方圏フィールド科学センター 和歌山研究林)
シカをドライブするサルたち
ヤクシマザルがヤクシカに与える影響をさまざまな空間スケールにおいて検討した。
自動撮影カメラによって屋久島各地のシカ密度を調査し、シカ密度に与える植生タイプ、駆除・狩猟圧、ノイヌ、そしてサル密度の影響を分析した。その結果、サルはシカ密度に強い正の影響を与えていることが示された。マクロスケール(個体群レベル)では、シカの生息密度分布にサルが重要な役割を果たすことが示唆された。
次に、メソスケール(地域レベル)におけるシカの空間配置に対するサルの影響を検討した。屋久島西部の照葉樹林内を踏査し、シカとサルを発見した位置を記録した。その結果、シカはサルの20m以内で多く発見される傾向がみられた。サルはシカのテンポラルな空間配置にも影響を与えていると考えられた。
ミクロスケール(個体・資源パッチレベル)でのシカに対するサルの影響を調べるために、個体識別したシカを追跡して観察した。シカがサルと20m以内に近接していた時間割合は7-9%であり、シカは必ずしもサルに追従しているわけではなかった。シカがサルに近接するのは、サルが落とす食物を得るためと考えられた。シカの採食時間に占めるサル由来の食物の採食時間割合は1割程度だったが、それらは比較的高質な食物と考えられた。サルの採食パッチの下にはサルが落とした食物を得るためにシカが集まることがあった。そこでは、シカ同士の敵対的交渉が起きる頻度が非常に高まっていた。この敵対的交渉ではオトナオス、オトナメス、未成熟個体の順に強かった。また、採食競合が起きていることで、個体により異なる採食戦術を採っていた可能性があった。
以上のようにサルはシカの生息密度分布、テンポラルな空間配置、採食行動や社会関係に大きな影響を与えているといえた。
辻大和(京都大学 霊長類研究所)
"DEER" FRIENDS: 食物を巡るジャワルトンとルサジカの種間関係
「落ち穂拾い行動」は、霊長類が樹上から落とす植物を地上性の動物が採食する関係をいい、これまでにアジア・アフリカ・中南米から報告がある。サルが樹上から落とす植物の多 くは、地上性の動物が本来利用できない食物資源であることから、この行動は、地上性の動物の採食成功、ひいては繁殖成功を高めている可能性がある。しかし「落穂拾い行動」の採食面での利益について定量的に評価した研究例は乏しく、同所的に生息する動物種の、食を介した結びつきに関する理解は不十分である。
2010年から2012年にかけて、インドネシア・ジャワ島のパンガンダラン自然保護区で野生ジャワルトン (Trachypithecus auratus) とルサジカ (Cervus timorensis) の間で見られる「落ち穂拾い行動」についての調査を行い、この行動の、シカにとっての利益を評価することにした。2年間で通算808時間の行動観察期間中、シカによる「落ち穂拾い行動」は93回観察された。この発生頻度の高さは、ルトン・シカの両種がいずれも高密度で生息していることに由来すると考えられる。ルトンが落とした植物のうち、シカに採食された植物は22種25品目にのぼり、その大部分は葉だった。ルトンが樹上から落とす植物の栄養価は、シカ本来の食物である草本類のそれと大差はなかったが、林床の単位面積当たりの食物量を大きくする効果があった。ルトンが採食中の木の下に集まってくるシカの平均個体数は、通常時と変わらなかった。「落ち穂拾い行動」 は降水量が少なく、草本類のバイオマスが低い乾季に頻繁に発生した。写真撮影によってルサジカの臀部の脂肪蓄積の度合を評価したところ、栄養状態は乾季に良好で雨季初期に悪いことがわかった。
パンガンダランにおけるシカの「落ち穂拾い行動」は、降雨量の季節変化が直接の引き金となって生じる、草本類のバイオマスの季節変化に起因すると考えられる。樹上から食物を提供してくれるルトンの存在は、地上の草本類が次第に減少し、蓄積した体脂肪に依存せざるをえない乾季のシカの採食成功にいくらか貢献しているだろうが、雨季にはその度合いが低下すると考えられ、その意味でシカにとってルトンは「必要不可欠な存在」というよりは「いればなお良い存在」だと考えられる。
大井徹(森林総合研究所)
採食行動の比較からツキノワグマとニホンザルの種間関係を考える
ツキノワグマとニホンザルは、比較的大きな身体を持ち、長寿命、半地上性、植物食中心の雑食性という比較的似かよった特徴を持つ日本の代表的な哺乳類です。一方、全く別系統の生物で、身体の体制や社会性等は大きく異なります。
このような特徴を持つ両種の現在の分布は冷温帯林を中心に重なっており、食物をめぐって競争関係にある可能性があります。また、クマは肉食獣の体制を持つのでサルの捕食者である可能性もあります。
しかし、競争の実態や捕食について事例すらありません。この2種の種間関係などほとんど誰も考えたことがないでしょう。しかし、両種の種間関係を考えることは、なぜ食物が似通ったそれぞれかなりのバイオマスのある異種が同所的に生息しうるのか、冷温帯落葉林の環境収容力や、種間関係、種内の個体(集団間)関係がどんな生態学要因によって規定されているのか、生態学の基本的問題について検討するためによい思考実験になるかもしれません。しかし、まずは、主に既往の文献に基づいて2種の採食生態をすなおに比較してみます。食性、食物資源パッチの利用の仕方、行動圏の面積、その利用パターンが比較項目です。その上で、この2種の種間関係を考えてみます。

 そのほか
そのほか